やまももは、漢字で楊梅と書き、中国や日本を原産とするヤマモモ科の常緑広葉樹です。
徳島県では、「県の木」に指定されており、高知県では「県の花」になっています。
古代の染料として、紫草や茜、紅花や藍などがありますが、楊梅も、古くから染色に用いられてきたものの一つです。
楊梅の樹皮をモモカワ(楊梅皮・桃皮)と読び、江戸時代には代表的な染材の一つとされていました。
目次
楊梅(やまもも)とは?

楊梅,ヤマモモ,Yoshio Kohara, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons,Link
楊梅は、木の高さが6m〜20mほどになり、葉っぱは深緑色で4月ごろに花が咲きます。
花が散ると、直径1cm〜2cmのイチゴのような丸い果実ができます。甘酸っぱい味がしますが、傷みやすいため遠くへの輸送が難しく、産地以外で市場に出回りづらい点があります。
白楊梅と呼ばれる薄ピンク色のような果実がなる楊梅は、昔から聖梅や水精やまももなどといい珍重されたようです。
根っこには根粒菌が共生していて、空気中の窒素を養分として取り込む能力を持つので、やせ地でも良く育ち土壌を豊かにする能力があるため、荒地を緑化する砂防樹としても適しています。
染色・草木染めにおける楊梅(やまもも)・渋木(しぶき)
楊梅の皮である楊梅皮は、日本において奈良時代には染色に用いられていたと考えられていますが、いつ頃から使用されていたのかはっきりとはしていません。
ただ平安時代には、楊梅色という色名があったと言われています。
天平5年(733年)に完成した『出雲国風土記』には、楊梅が記載されており、諸国から貢進された品目の一つとされています。
鎌倉時代に装束について書かれた有職書である『餝抄』には、「永保三四十三御禊前駈左衛門権佐為房八葉細代不開物見楊梅色革鞦伊知比遣縄」とあり、楊梅色と言う色があったことがわかります。
薬用であるとともに、染料としても使用されていたものと考えられ、正倉院宝物として現存する薬物の中には、染色に使用されたものも多く残っています。
室町時代になると楊梅を用いた黒染めが盛んになり、江戸時代に入ってからは、桃皮といわれ、茶色系統の色に使用されていたことが『紺屋茶染口伝書』(1666年)などの染めものに関する書物に記載があります。
楊梅の皮から採取した染料は、「渋木」などとも呼ばれました。
成分として、多量のタンニンやミリセチンやミリシトリンなどのフラボノイド色素を含むため、染料としての効果があります。
楊梅皮は、煮出しただけでは薄くて明るい感じの茶色ですが、媒染剤の量や種類によって多様な色に染められます。
染色堅牢度を高めるために、蘇芳などの下染に使う染料としても重宝されました。
ミョウバンを使うと黄色系統で、鉄分で黒っぽくなり、鉄と石灰を使用すると赤みのある茶色、銅を使うと黄色に茶色を混ぜたようなカーキ色になります。
浸染や引き染め、注染など幅広く染色応用されてきました。
江戸時代中期、医者であった寺島良安によって編集された百科事典である『和漢三才図会(1712年)』には、「楊梅は薩州より出る者良し、汁を煎じて黄褐茶色を染む、又漁網を染むれば即ち久しく䶢水に耐ふ、柿渋と同じき故、渋木と名づく」とあります。
つまり、上記では、鹿児島県の楊梅が良く、漁の網を染めれば、海水に耐えるということをいっています。
『絵具染料商工史』(1938年)には、桃皮や渋木の名前で、黄褐色を染める染料として、江戸時代に大阪の染料屋で取り扱われていたようです。
江戸で好まれた黄味の暗い茶色(江戸茶色)を染めるため、楊梅が使用されていました。
鉄がサビたような黒味のあるくすんだ朱色は、「錆朱色」と呼ばれることがありますが、この色合いは蘇芳と楊梅で染められました。
灰汁媒染による楊梅染め
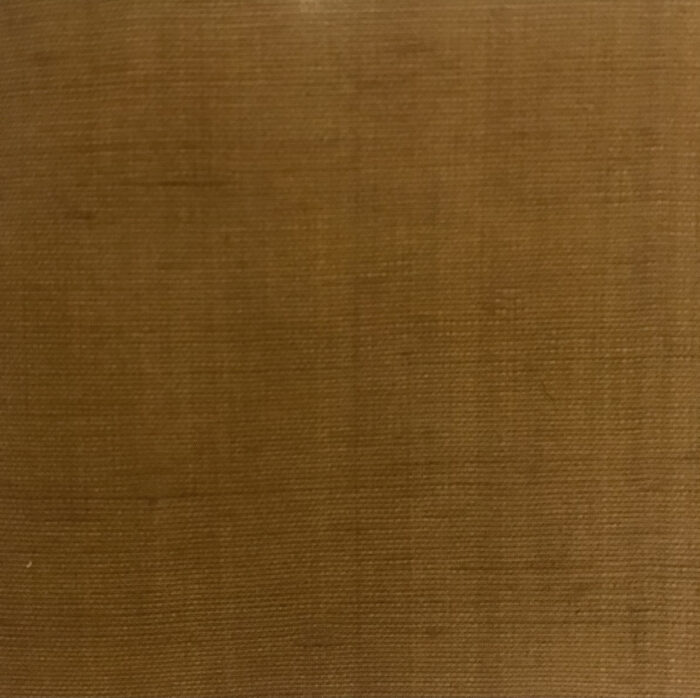
楊梅(やまもも)で染めた色合いの一例
木灰からとった灰汁を媒染剤として使用した楊梅染の一例としては、以下のような流れになります。
関連記事:草木染め・染色における灰汁の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か?
①絹糸1kgを灰汁6リットルに浸して、先に媒染しておく
②細かく刻んだ楊梅の樹皮500gを6リットルの水に入れて熱し、沸騰してから20分間熱して煎汁をとり、同じようにして4回まで煎汁をとる
③染液を熱し、灰汁で先媒染した糸を浸し、20分間煮染したあと染液が冷めるまでおいておく
④糸をしっかり絞ってから、天日の元で乾燥させる
⑤灰汁6リットに乾かした糸をつけておく
⑥さらに濃くする場合は、4回まで煎汁をとった樹皮を用いて、8回まで煎汁をとる
⑦5回〜8回の煎汁を熱し、灰汁に浸していた糸をしっかり絞りさばいてから、20分間煮染し、染液が冷めるまでおいておく
⑧しっかり水洗いしてから天日に当てて乾かし、色合いによっては再度灰汁に浸してから仕上げる
楊梅(やまもも)の歴史
中国において、楊梅は古くから食べられており、日本の古文書『出雲国風土記(733年)』には、楊梅の記載があります。
平安時代(794年〜1185年)には、果物として、山城(現在の京都府南部)、大和(現在の奈良県)、摂津(現在の大阪府北西部と兵庫県南東部)などから献上されたと『延喜式(927年)』に記載されています。
関連記事:古代日本人の色彩感覚を延喜式から読みとる。衣服令(服色制)と草木染めについて
そのほか、大和物語(951年頃)や清少納言が書いた枕草子(995年〜1010年頃)、平家物語などにも記述があり、古くから日本においても大事にされてきた植物であることがわかります。

大和物語,Ogata Gekkō, Public domain, via Wikimedia Commons,Link
大和物語では、藤原忠文の息子である藤原滋望が父とともに東国へ下ることになったとき、滋望と交際していた監の命婦が楊梅を贈ると、滋望は命婦に「みちのくの あだちのやまも もろともに こえばわかれの かなしからじを」と詠みました。
監・・・近衛府の将監。女性を呼ぶときに親兄弟の官職を付けて呼んだ。
命婦・・・宮中や後宮の女官。平安時代以後は中級の女官をさす。
薬用としての楊梅(やまもも)
薬用としては、中国で973年に刊行された医薬に関する本である『開宝本草』に記載あります。
中国では果実を薬用とし、痰をとり、嘔吐を止め、アルコールによる影響を緩和する効果などがあるとされてきました。
日本においては、7月下旬~8月上旬にかけて赤褐色(赤みを帯びたオレンジ色のような色)の樹皮を「楊梅皮」と呼び、使用してきました。
樹皮は、タンニンや強い抗酸化作用をもつミリセチンやミリシトリン(フラボン配糖体)を含んでいます。
煎じて下痢などのお腹の調子を整えたり、殺菌や止血作用があるとされ、火傷や皮膚のできものなどの皮膚病に使用したり、捻挫や打撲に粉末を塗ったり、殺虫や解毒薬としてなど民間療法的に用いられてきました。
元禄10年(1697年)に刊行された『本朝食鑑』には、楊梅の果実で作られた「楊梅酒」は「食を消し、悪気を除く」との記載があります。
具体的には、楊梅酒は不眠や貧血、冷え性や食欲増進、疲労回復などに効果があるとされます。
【参考文献】
- 『月刊染織α1981年6月No.3』
- 『月刊染織α1992年10月No.139』
