葛は(学名:Pueraria lobata.)は、日本全土で見られるマメ科の多年草で山地や野原など、至る所に生育しています。
長いつるを伸ばして他の草木を覆い隠すので、厄介な雑草として扱われることもありますが、葉は牛の飼料になり、根からは上質なデンプンである葛粉が取れたりと、様々な分野で活用されてきた有用植物です。
葛布(くずふ)とは?

型染めされた葛布(くずふ)
葛布とは、葛の繊維で織った織布のことを表し、いわゆる植物の茎を用いる靭皮繊維を原料糸とした織物の一種です。
葛布には底辺的なものと、貴族用の高級織物が存在し、「水干葛袴」の名前が残っていることから、袴としての用途が続いたことがわかります。
目次
葛布の特徴
葛布は、外見や手ざわりが麻と似ていますが、実際には性質に違いがあります。
葛布は、繊維自体が光沢感があり、軽くて雨に強く、水切れが良いものの保温性がある点が特徴として挙げられます。
一般的な麻の繊維は放熱性があることにより夏物衣類に適していますが、葛布はその保温性によって、着物の上に羽織る上着の一種である被布や合羽、裃、敷布などにも仕立てられました。
葛布に施された柄は、白無地以外にも、経糸の木綿を染めて縞柄を入れたり、白無地に織り上げてから黒や紺、浅葱、萌黄、鉄、鼠、茶などで後染めしたり、小紋染めなど型染めを用いて染められました。
葛繊維の特徴
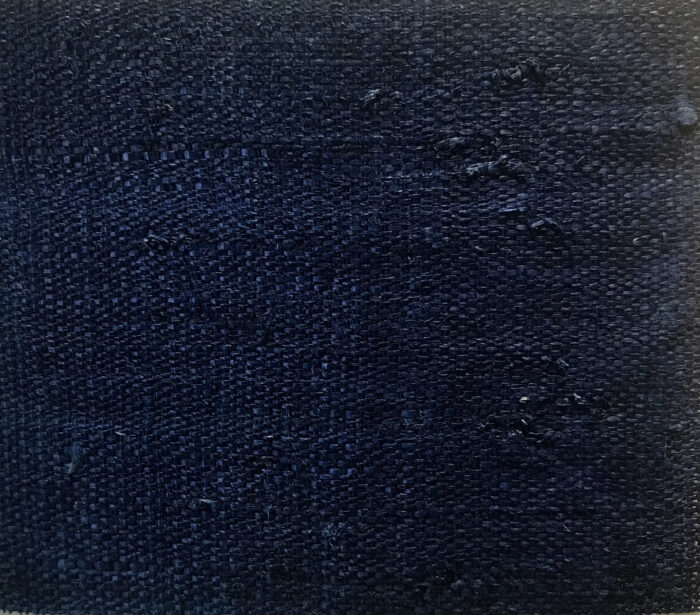
藍染された葛布
葛は、どのような荒地にも生育しますが、いくらか湿地を好みます。
樹木にからみついているような葛は、長くそろった繊維が必要な織物には向きません。
日陰から日向に向かって、斜面をはって真っ直ぐに延びたものが良いとされ、節が少なく、やわらかで、光沢があり、肉が薄いものが上質であると考えられます。
秋に入ると繊維が硬くなるため、刈採りは、5月下旬から9月頃までの期間で行われ、採取される順番に一番つる、二番つる、三番つる、四番つると呼ばれました。
秋になるとつるが強張り(柔らかいものが硬くなる)、繊維として使用するのが難しくなります。
葛の繊維は、藤と同じように強度やしなやかさを持ちます。
葛繊維の特徴としては、繊維は白く光るような金属的な光沢があり、繊維が薄いため軽く保温性もあるため、高級織物としても使われてきました。
ただ、乾燥に弱く、撚りをかけると切れ易いため、藤の繊維ほど利用されなかったとも考えられます。
折れやすい経糸は、絹や麻、木綿に変更し、緯糸に撚りをかけていない葛繊維にすることで、織りやすくする工夫もされてきました。
経糸と緯糸に葛を使う織物も、佐賀県の唐津市佐志などで織られていました。
葛布の技法

葛布(くずふ)
5月末頃に刈り取っておいた葛の蔓を束にして、熱湯の中で5分〜6分煮ます。
煮た後に水に浸けて、一昼夜おいたものを、ススキの青草の中に入れて床を作り、繊維を発酵させます。
表面がドロドロになった繊維を水洗いし、靭皮だけを取り出して乾燥させ、これが葛苧となります。
葛苧をさらに細かく裂いて、糸に紡いでいきます。
染色は、糸染めと後染めがあり、古くは天然の藍染や草木染めが行われていました。
製織は、葛糸は弾力性がないため、緯糸に用い、経糸は木綿糸か麻糸が用いられます。
織り機は、元々は居坐機と呼ばれる最も原始的な機が使用されていました。
織り上がった葛布は、木槌で砧打ちし、繊維を柔らかくし、裏に糊を引いて仕上げられます。
葛布の歴史

葛布(くずふ)
葛の繊維利用は、織物の歴史においての最も古い部類に属していいます。
例えば、7世紀後半から8世紀後半(奈良時代末期)にかけてに成立したとされる日本に現存する最古の和歌集である『万葉集』には、4,500首以上歌が集められていますが、その中にも、葛布を詠んだと思われる歌が二首あります。
「劔太刀鞘ゆ納野に葛引く吾妹真袖もち着せてむとかも夏草刈るも(1272)」
「女郎花生ふる沢辺の真田葛原何時かも絡りてわが衣に着む(1346)」
『延喜式』にも葛布の記載があり、10世紀初頭頃のことです。
平安時代初期の文献には、宮中の蹴鞠遊戯に着用する奴袴として、朝廷に献上されたことが記されていたり、鎌倉時代以降は、繊維の丈夫さから「葛袴」と呼ばれる武士の馬乗袴としても盛んに用いられてきました。
鎌倉時代以降から、江戸時代末期まで武士の夏袴地などに多く用いられ、「葛袴」とも呼ばれていました。
葛布のシャキッとした折り目正しさが、武人の心をひきつけたとも考えられます。
鎌倉時代後期ころに成立したとされる軍記物語である『源平盛衰記』の「三十三」に源頼朝は「布衣に葛袴を着せり」という記述があります。
「征夷大将軍の宣旨」を携えて京から下向した朝廷の使者をもてなすという晴れがましい場面で、頼朝が堂々と葛布の衣装を着用しているのです。
木綿が日本において普及する前は、仕事着の材料として葛布が重宝されていました。
江戸時代には、全国各地で葛布が織られていて、袴地や裃、蚊帳や座布団などとして広く用いられていました。
葛布の産地
葛布は、特産的なものではなく、古くは東北から九州まで至る所で生産されたと考えられますが、「本場物」として現在の静岡県掛川に定着しました。
近世、経糸に木綿糸を使用した葛布を名産的に織り出したのが、掛川だったのです。
「大日本物産詳解」には、「掛川の名産となれるは遠く寛文年間の頃よりなり」とあったり、「和漢三才図会」には、「葛布は遠州懸川より出づ」とあり、経糸が木綿で緯糸が葛の葛布が定着したのは、寛文(1661年〜1673年)から正徳(1711年〜1716年)という17世紀後半から18世紀初め頃と考えられます。
東海道掛川の街道に沿って何軒もの織屋が「名産葛布」と書かれた看板を軒下につるし、行き交う旅人たちに売っていたとされています。
掛川では、葛布を「クズヌノ」と訓読みせず、「クズフ」と重箱読みするわけでもなく、「カップ」と音読みする習慣があったようです。
明治維新による葛布生産の変化
19世紀後半の江戸時代末期から明治維新にかけては、どの分野においても大きな変動期であり、転換期でした。
葛布は、地機で織られ、葛のつるの採集から織り上げまで一貫して自家生産の形で作業が行われました。
他方、取り出された繊維(葛苧)の状態にした葛を農家から買い取って、機織りだけ行う形もありましたが、織り上げられる布はもっぱら小巾の布でした。
明治維新による世の中の変動で、武家階級が転落し、武家向けの袴地の需要が急激に減少していきました。
それによって、葛布産業の生産様式が急転したことで壊滅状態になり、多くは問屋は転業していきます。
また、近代繊維産業の発達によって葛布が衣料としてほとんど用いられないようになりました。
ただ、葛布を捨てきれない人々によって、小巾から三尺巾(約90cm)が織れる高機に移り、葛布としての用途を広げました。
小巾から大巾への転換は、明治初年には始まっていたようで、明治17年(1884年)〜18年に襖地や壁紙(壁装材)、屋内装飾用品に活路を見出します。
明治30年代頃からアメリカ向けに、壁紙(壁装材)としての輸出が始まり、好評だったことから生産がいくらか安定していきます。
江戸時代のような藩ごとにブロック経済を築き、各藩が保護政策をしているような状況ではなく、交通がひらけ、輸出が盛んになると北は青森から南は九州や四国の各地から葛が採集され、掛川に集まりました。
繊維の質的には、掛川を中心に富士山麓や伊豆のものが優れていたようです。
ただ、朝鮮から輸入された葛苧(葛のつるから取り出された繊維)は、肉厚で光沢が少なく、上物にはなりませんでしたが、安価なため、その利用が需要の9割を占めるようになりました。
太平洋戦争と戦後の混乱における葛布
太平洋戦争と終戦の混乱ののち、アメリカへの葛布の輸出が再び始まりますが、長くは続きませんでした。
韓国では、自国の産業として葛布を織った方が有利であると気が付き、葛布がさほど高度な技術を必要とする織物ではないことがわかると、自国で生産を開始します。
韓国からの日本への原料の輸入が止まり、その他様々な外的要因も相まって、掛川を中心として葛布生産は壊滅的な打撃を受けました。
【参考文献】岡村吉右衛門(著)『庶民の染織』
