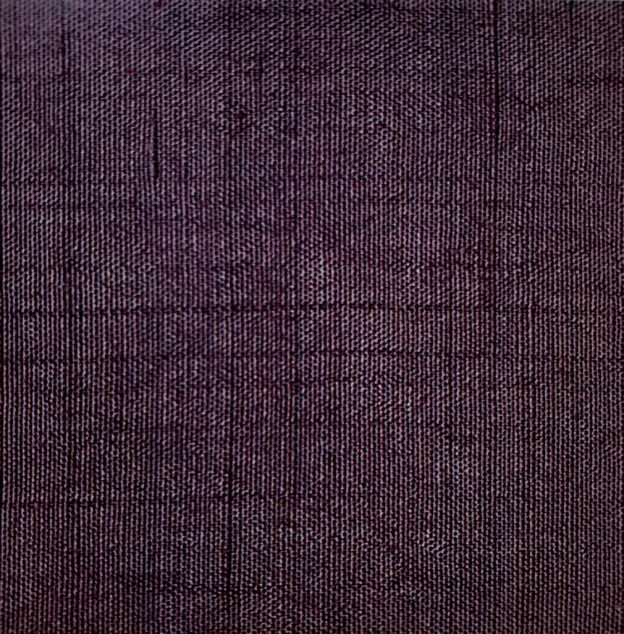紫根を使って灰汁媒染で染めた紫色の衣類が、紫衣と呼ばれていました。
中国では、古くから紫色は、間色として遠ざけられていましたが、やがてその色の美しさから尊ばれるようになり、この考えが日本にも伝えられます。
日本では、飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である『衣服令』が存在していました。
この制度は、中国の唐代の服飾に影響されて制定されたもので、603年の冠位十二階、647年の七色十三階制、701年の大宝律令などいくつかの服色制を経てきました。
『衣服令』などからわかるように、紫色は、飛鳥・天平時代以後においては、天子・皇太子を除いて、臣下としては最高の位の人の衣服の色となっています。
なお、茜染の朱衣も、極めて濃い色は、多少の鉄分などの影響でやや紫味をもつことがあるため、時として紫衣と書かれることがあったようです。
緋色の衣類が朱衣と呼ばれ、本来は茜染された着物のことです。
灰汁媒染で染めた色が、あたかも朱のような黄赤色であったので、これを朱衣といったのです。