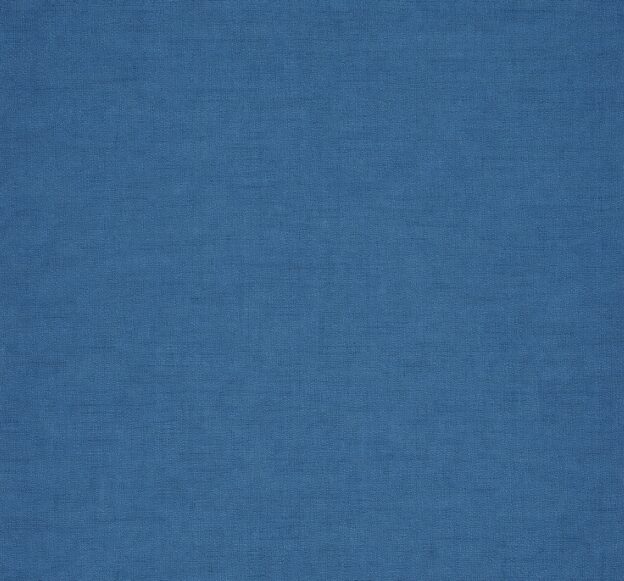藍は、古くから世界各地で使用され、人々に一番愛されてきたともいえる植物染料です。
日本において、藍染された色は一番薄い藍白から、一番濃い留紺まで、「藍四十八色」と呼ばれるほど多くの色味があり、それぞれ名前がつけられていました。
それぞれの藍色に名前をつけて区別をしようと思えるほど、藍色を見る目を昔の人々が持っていたともいえます。
日本の伝統色とされる数々の色の中でも、藍色、紅色、紫色の3つの色は歴史や色の豊富さなど、日本人にとってとりわけ関わりが深く、日本を代表する色であったといえます。
藍染で濃く染めることによって布自体の丈夫さが高くなり、また縁起の良いものとされていたため、古く、武将が好んで濃色に藍染された衣類を着用していました。
一方、藍染された淡い色も人々には好まれ、京都においては「京の水藍」という言葉が江戸時代の文献に残っており、色合いがあざやかで品質が高かったとされ、水藍の色は京浅葱(淡い水色)とたたえられていました。
藍染された色合いである縹色(はなだいろ)・花田色
暗い青、鈍い青に対して用いられた古い色彩名に縹色(花田色)があります。
縹色(花田色)は、『日本書紀』(720年)の持統天皇の条に「深縹」、「浅縹」という色名があらわれます。
『阿州藍奥村家文書 第五巻』に記載されている、「蜂須賀逢庵光明録」には、縹色について下記のような記述があります。
元明帝の和銅七年(714年)に始めて染殿を造り藍草を以て衣服差抜(指貫)を染め花田色(今の水浅葱色にて後に花色といふ)を稱して位を白衣の次に置き三位以上の服色と定め下司等をして濫りに用ひざらしめず其頃は花田色を以て五色中の最上を爲せり
上記では、元明天皇の和銅七年(714年)に、はじめて染殿が設けられ、 藍草を用いて衣服の指貫を染め、 その色を花田色(現在でいう水浅葱色で、のちに「花色」と呼ばれる)と名づけ、この花田色は、服色の序列において白衣の次に置かれ、 三位以上の者が着用する服色と定められ、 下級官人などが勝手に用いることを禁じたというような意味です。
当時、花田色は五色(青・赤・黄・白・黒)の中でにおいて、 花田色=青系が「最上」とされていたようです。
延喜式における縹色
養老の「衣服令」では、「八位深縹衣、初位浅縹衣」とあり、低位の色だったとされます。
平安時代中期以降は、六位の袍の色と定められます。
養老律令の施行細則をまとめた『延喜式』(927年)には、深縹、中縹、次縹、浅縹の記載があります。
深縹は、「綾一疋に藍十囲薪六十斤」、中縹は「綾一疋に藍七囲薪九十斤」、次縹は「帛一疋に藍四囲薪六十斤」、浅縹は「綾一疋に藍一囲薪三十斤」を用いて染めるとあります。
深縹は、紺色のように少し赤みを帯びていた色とされ、浅縹は一般的な縹色で、俗に「花色」とも呼ばれます。
『万葉集』には、水縹という名称があり、これは非常に淡い藍色と考えられます。