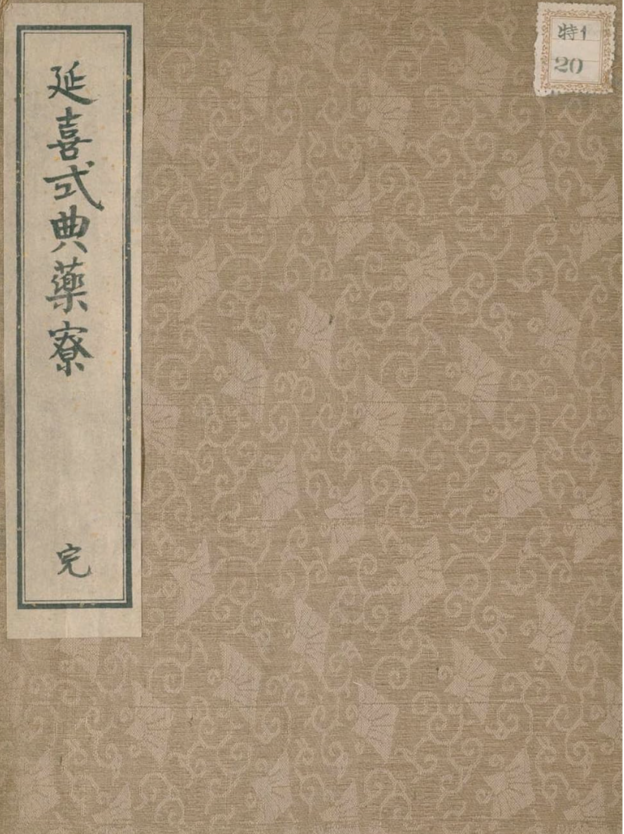日本の古代の人々は、草木が成長し花が咲き、果実が実るのは、草木に宿る精霊(木霊)の力であると信じ、草木からとれる自然の色で、衣服を染めつけていました。
強い精霊の宿るとされる草木は、薬用として使用されていました。薬草に宿る霊能が、病気という悪霊によって引きおこされた病状や苦痛を人体から取り除き、悪霊をしりぞける作用があるとされていたのです。
染色の起源は、草木の葉っぱや花などを摺りつけて染める「摺染」です。
日本の染色技術が飛躍的に発展するのは、4世紀ごろに草花から染料を抽出し、これを染め液として、浸して染める「浸染」の技術が中国から伝わってきてからです。
衣服の色によって位階に差をつける衣服令(服色制)
日本では、飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である『衣服令』が存在していました。
この制度は、中国の唐代の服飾に影響されて制定されたもので、603年の「冠位十二階」、647年の「七色十三階制」、701年の「大宝律令」などいくつかの服色制を経てきました。
平安時代(794年〜1185年)に入ると、日本独特の色彩名が定められ、染色技術も確立したとされます。
日本では、757年に律令国家におけるルールを規制した「養老律令」が施行されましたが、その養老律令の施行細則をまとめた『延喜式』(927年)には、染織物の色や染色に用いた染料植物が詳しく書き残されているのです。
染色・草木染めにおける『延喜式』(えんぎしき)
『延喜式』は、平安時代にまとめられた三代格式の一つです。
『延喜式』は、AmazonのKindle Unlimitedに登録すると、kindleで無料でデータを読むことが可能です。
延喜年間(900年代の初年頃)に勅命(天皇の命令)によって制定されることになった「式」、すなわち「制度」であるというのでこの『延喜式』という名前があります。
三代格式のなかでは、ほとんど完全な形で今日に伝えられているのは『延喜式』だけであり、奈良、平安時代の国家制度を知る根本法典として、日本古代史の研究に不可欠な文献となっています。
『延喜式』のなかの「縫殿寮」や「雑染用度条」というところに、染められた織物の色彩名と、染色に用いられた染料植物が詳しく書き残されています。
そのため、古い染色を研究する人たちにとっても、欠かすことのできない文献となっているのです。
しかし、注意点としては、この文献は当時の原本は伝わっておらず、今知られているものはかなり後の写本であり、しっかりと検討してみないと、いろいろな間違いや記載漏れがあるため、そのままで解釈すると間違った結果になる可能性があります。
階位によって定められた服色があったので、『延喜式』にはその色を染める材料や数量が示されており、色彩名と使用された染料植物はさまざまでした。
以下の画像は、「衣裳を彩る色材の分析―日本における染色の歴史と琉球紅型衣装にみられる色材―」にまとめられているものからの引用です。
- 韓紅花・・・紅花
- 中紅花・・・紅花
- 退紅・・・紅花
- 深蘇芳・・・蘇芳
- 浅蘇芳・・・蘇芳
- 浅緋・・・茜
- 緋・・・茜
- 深紫・・・紫草
- 浅紫・・・紫草
- 深滅紫・・・紫草
- 深緋・・・茜と紫草の重ね染
- 黄支子・・・支子(梔子)
- 黄丹・・・支子と紅花の重ね染
- 深黄・・・刈安
- 浅黄・・・刈安
- 深縹・・・藍
- 中縹・・・藍
- 浅縹・・・藍
- 深緑・・・藍と刈安の重ね染
- 浅緑・・・藍と黄檗の重ね染
- 黄櫨・・・櫨と蘇芳の重ね染
- 橡・・・カシ・ナラガシワ・クヌギ
支子と紅花の重ね染めされた色である、黄丹は皇太子のみが着用することができた衣類(袍)の色として、また櫨と蘇芳の重ね染めされた色である黄櫨は天皇のみが着用できる袍の色として「禁色」にされていました。
『延喜式』に記載されていた植物染料の数はそこまで多くはありませんが、色を重ねて染める「交染」の工夫がされて、多彩な色が生み出されていました。
延喜式の染めを復元した『式内染鑑』(しきないそいめかがみ)
「延喜式」の「縫殿寮」の中の「雑染用度条」の規定には、上記で述べたようにさまざまな服色の染め方を記した部分がありますが、そこに記された染め方を、徳川八代将軍の徳川吉宗(1716年〜1745年)が、膨大な費用と多くの人材の結集によって、長い間復元した記録に『『式内染鑑』があります。
染色の作業は、小納戸(将軍の身辺の雑務を担当)の浦上直方と呉服師の後藤縫殿助を中心に、享保14年(1729年)に江戸城の吹上庭園内に設けられた「染殿」で作業が進められ、多くの古代の染色の復元に成功しました。
徳川吉宗の治績や逸事を記した『有徳院殿御実紀附録』に「縫殿式の染色、半にすぎて染出しければ、この服色をあつめ帖とせられ、式内染鑑となづけて、後の証とせられしが」とあり、『式内染鑑』には、染殿で染色した色の実物の色見本がつけられていたことがわかります。
ただ、世に知られているものはすべて写本であり、当時の染色をそのまま伝えていないと思われるものが多くあります。