紋というと、基本的に「家紋」を表し、代々その家に伝わる家の印として、家系や個人を識別し、その地位を表すために使われてきました。
紋には、正式の紋と略式の紋があり、略式の紋は正式の紋の一部であったり、全く別の簡単な図柄を使うこともあります。
紋はもともと武家の男子に用いられていましたが、江戸時代中期以降に、武家の女子にも使い始められ、彼女たちの小袖の背中と両袖に1つずつ染め抜かれるようになりました。
目次
家紋(かもん)の起源と歴史
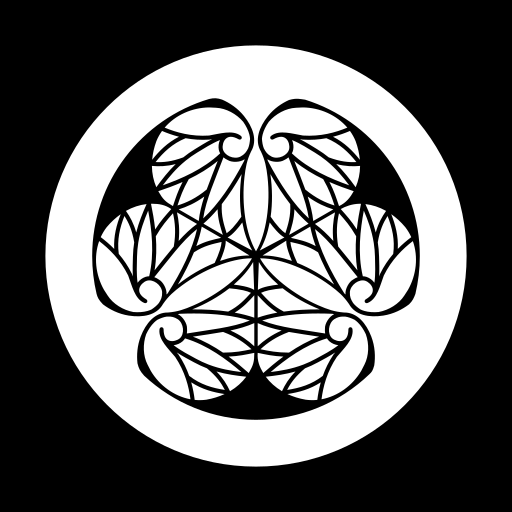
尾張徳川家三つ葵の図例/Mukai, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons,Link
家紋の起源は、一般的に平安時代に社会的な特権をもった公家が用いた牛車(ぎゅうしゃ)に、それぞれの家の好みの模様(文様)を描いたことからとされています。
牛車の模様(文様)は、家の誇りを示す意識という点では家紋の場合と同じ役割があります。
特定の集団や一族などを他と識別するという家紋の明確な役割のために、紋が作られるようになったのは、鎌倉時代からとされます。
鎌倉時代初期から武家が戦場での目印として、遠方から見分けやすい単純な図形を旗につけ始めます。
次第にその図形は、単なる目印として以上に、特定の呪術性や宗教性、精神性などの意味をつけ、デザインも複雑化していきました。
一つの集団の中でも、個人の目印として細分化する傾向もあり、各人の武装につける紋の種類は非常に多くなり、個人の好みに反映した自由な模様(文様)も生まれます。
武装に限らず、衣服にも家紋がつけられ、直垂に大きな紋をつけた「大紋や、肩衣や袴、小袖などの決まった場所に紋をつけるという現在と同じ使われ方がされるようになります。
武家の家紋
中世では、御恩と奉公といったように、武家社会において主人とそれに使える従者が、相互に利益を与え合う互恵的な関係で成り立っており、その連帯感を強めるためには、家柄や家の誇りを紋という見える形で共有する必要があったのです。
武家の紋は、旗や盾、陣幕などの印として表され、戦国時代から盛んに衣類に付けられるようになったと推測されています。
例えば、現在の埼玉県熊谷市を本拠地とし、平安時代末期から鎌倉時代初期に活躍した武将の熊谷直実は、八幡大菩薩の使いとされた鳩と、武士や庶民が好んで用いた寓生を組み合わせて紋として、それを自分の着物にもつけたようです。
武家の紋には、熊谷直実のように具体的なデザインのほかに、ただ単に一、二、三などの数字や+、○のようなシンプルなものや、幾何学的な図形のようなものが用いられました。
公家(くげ)の家紋
公家も武家の影響を受けた後に、家紋を使うようになりました。
皇室の御紋章である菊花紋章(きっかもんしょう)は、後鳥羽天皇が菊を特に好まれたため紋章にしたという話もありますが、菊の花の形が美しく整っており、なおかつめでたいことが起こるという前兆(瑞祥)としての意味を表すことから選ばれ、使われたものと考えられます。
御紋章として描かれたはわかりませんが、13世紀の鎌倉時代に描かれた、北野天神を題材とした絵巻『北野天神縁起』の中には、菊花が宮中の象徴として描かれていることが知られています。
江戸時代における家紋
江戸時代には、戦場での識別という実利的な目的が失われ、武家社会で先祖の武功や家の格式を示したり、行列のための装飾としての形式的な目的が主となりました。
江戸時代に入ってから、図形を単純化したものやシンプルな文様などがよく見られるようになりました。
戦乱の世から、徳川家康が幕府を開き、平和が長く訪れると、戦場での印の意味合いが薄くなり、家系を誇り、威厳を示すことが主な目的になりました。
家紋の下賜(高貴の人が、身分の低い人に物を与えること)や譲与も行われ、名誉の象徴としても使われました。
家紋が格式化するとともに紋付の衣服は、公的・儀礼的意味を持つようになります。
紋付とは、家紋の入った着物のことです。
家紋の種類は非常に多く、植物紋や動物紋、器物紋、天紋、地理紋、文様紋などに大別できます。
大名の氏名、家紋、所領などを一覧にした家系図や諸家譜である『大名紋尽し』や、大名・旗本・幕府役人の名鑑である『武鑑』などが刊行されるようになったのをみると、紋をつけるという文化がよく発達していたのがわかります。
家紋に対して、私的趣味的な紋として装飾的に上品で美しい「替紋」や、略儀の時や私的な外出の際に定紋の代わりとして使った少しくだけた紋様である裏紋も新たに考案されます。
武家の女子の間で、紋付が着用され始めたのも太平の世が続いたこの頃です。
町人と家紋
町人のうち、庄屋や名主などの村役人で特別の業績を挙げた者や、行政に協力して功績があったものなどに、苗字帯刀を許されました。
苗字帯刀を許された町人は、その家柄を誇って家紋を使ったり、歴史ある商家の家では、商売の印である暖簾や着物にも家紋をつけるようになります。
また、役者が個人の好みや芸風を反映させて独自の家紋をつけたり、面白半分なものやオシャレなデザインが評価されました。
現在でも家紋は、紋付の衣服を主として、家具や調度品、墓石などに用いられますが、家族制度の崩壊とともに、本来の家紋の意味は失われつつあります。
紋付における紋の位置
紋付における紋の数は、一つ紋、三つ紋、五つ紋と数が増えるほど格が高いものとされています。一つ紋は背に一つだけ、三つ紋は背に一つと袖に二つ、五つ紋は背に一つ、袖前と前身頃に二つ付けます。
紋が表示する位置については、紋が指し示す効果や様式美の観点からも、理にかなっているものとなっています。
時は、鎌倉時代になり、公家に雇われていた下級官人が着用していた水干という上着における、補強と装飾をかねて組紐を通して結んだ菊綴と呼ぶものを、武家が直垂という上着に導入しました。
関連記事:武士、侍(サムライ)はどのような衣服を着ていたのか?武士の装いの歴史。
菊綴の位置は、両胸、背中、奥袖と端袖の縫い目、袴の両股立、前側の縫い目にあり、室町時代以降に、好みの大きな文様をつけて「大紋の直垂」、略して「大紋」と呼びました。
江戸時代になって、好みの文様つけていた部分が家紋に変えられて、大紋から変化した服で、室町時代がその始まりとされる素襖という上下セットの着物にも家紋をつけるようになったのです。
さらに素襖の袖を取り除いた形の裃や、大紋や素襖、裃などの下に着用する小袖や羽織なども、もともと菊綴をつけていた場所に紋所があります。
紋付羽織袴
紋付〇〇という言葉でよく聞くのが、紋付羽織袴です。
戦国時代から、武将が好んで胴服と呼ばれることが多かった羽織を着用していました。
関連記事:武士、侍(サムライ)はどのような衣服を着ていたのか?武士の装いの歴史について

新郎は紋付羽織袴、新婦は黒の引き振袖を着用/投稿者によるスキャン/Public domain/via Wikimedia Commons,Link
それから時代が下り、家柄を誇示したり、装飾目的で小袖に紋をつけたものが、羽織で隠れてしまうのはもったいないので、羽織にも紋をつけるようになったというのは必然だったのでしょう。
【参考文献】高田倭男 (著)『服装の歴史』