桜は、古くから人々に親しまれてきました。
7世紀後半から8世紀後半(奈良時代末期)にかけてに成立したとされる日本に現存する最古の和歌集である『万葉集』には、4,500首以上歌が集められていますが、桜を詠んだ歌が非常に多く、「桜の花」、「桜花」、「山桜」、「山桜花」などとあり、40首が収められています。
ただ、桜が染色に用いられるようになったのは近年になってからと考えられます。
江戸時代には「桜鼠」など色名がありますが、桜自体を使用したわけではなく、桜色がかった鼠色のことを指していると考えられます。
目次
染色・草木染めにおける桜(さくら)
山桜(学名Cerasus jamasakura)を染色に用いる場合、葉や樹皮、大木の幹からとった幹材や小枝を利用します。

山桜,Arashiyama, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,Link
媒染剤を使い分けることによって、色合いが異なってきます。
ちなみに馴染み深いソメイヨシノ(染井吉野)は、江戸時代末期に江戸の染井村の植木屋が売り出したことに由来し、エドヒガン(ウバヒガン)とオオシマザクラとの交雑種とみられます。
桜色(茶色味がかった赤色)を染める場合
桜を木灰に水や熱湯を混ぜてつくる灰汁(椿灰や酢酸アルミなどを媒染剤に使用すると、茶色味がかった赤色(桜色)を染めることができます。

桜染め,アルミ媒染
関連記事:染色・草木染めにおける灰汁(あく)の効用と作り方。木灰から生まれる灰汁の成分は何か?
絹糸を染める一例として、以下のような流れがあります。
煎汁をとる際に、灰汁を2倍に薄めたものor水1リットルに対して炭酸カリウム1gを入れたアルカリ水を用いるのがポイントです。
アルカリ水で煎汁をとった場合、中和しないと糸を痛めるだけではなく(絹やウール)、染まりづらいので必ず酸を使用して弱酸性にします。
ただ、酸性が強すぎると色合いが異なってくるので注意が必要です。
①山桜樹皮、大木の幹からとった幹材や小枝を1kgを細かく刻み、灰汁を2倍に薄めた8リットルの水に入れて熱し、沸騰してから20分ほど熱煎して煎汁をとる。同じようにして3回まで煎汁をとり、1番から3番までの液をまとめて染液とする
②染液phが6.5〜7ぐらいがよく染まるため、米酢や酢酸などを染液に少量加えて中和、弱酸性の染液にする
③染液を火にかけて熱し、絹糸1kgを浸して10分間煮染したあと、染液が冷えるまでか一晩染め液に浸しておく
④灰汁もしくは、酢酸アルミ40gを15リットルの水に溶かして、染め糸を浸して30分間媒染し、水洗いする
⑤染液を再び熱して媒染した糸を浸して15分間煮染し、染液が冷えるまで浸しておき、水洗いして天日の元乾燥させる
⑥さらに染め重ねる場合は、3回まで煎汁をとった桜を同じようにして、6回まで煎汁をとり、染液として、乾かした糸を再び浸し、15分間煮染し、染液が冷えるまでおいておく
⑥灰汁もしくは、酢酸アルミ40gを15リットルの水に溶かして、染め糸を浸して30分間媒染して水洗いする
⑦再び、染液を熱し、媒染した糸を浸し、5分間煮染したと、染液が冷えるまで浸しておき、水洗いして天日の元乾燥させる
紅鳶色(べにとびいろ)を染める場合
紅鳶色を染める場合、媒染剤にクロム、もしくは銅を使用します。
酢酸クロムを使用する場合は、糸量に対して2パーセント使用し、銅の場合は酢酸銅3パーセントを用います。

紅鳶色(べにとびいろ)
桜鼠(さくらねずみ)を染める場合
鉄を媒染に使用することで、桜鼠から鼠色に染めることができます。
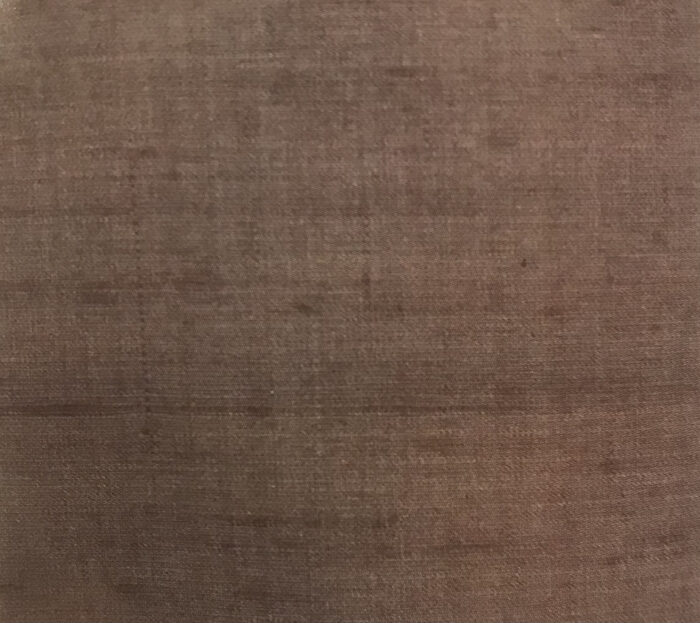
桜鼠(さくらねずみ)
【参考文献】『月刊染織α1985年12月No.57』
